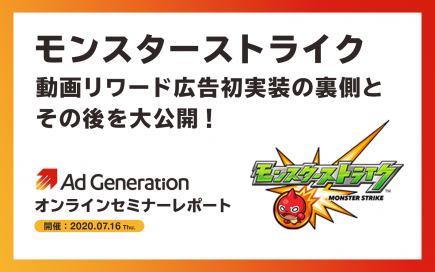ブランディング広告などに対し、「短期的な売り上げを追いかけるためのもの」と考えられがちなダイレクトマーケティング。しかし、ECが浸透し、テクノロジーの進化により多様なデータを収集・分析・活用できるようになった昨今では、ダイレクトマーケティングは事業を中長期的に成長させるために注力すべき施策であるといえます。
今回の記事では、Supershipのプロダクトマーケティング室長として、マーケティング事業の戦略立案を手がける小嶋 泰我が、「中長期的に事業を成長させるためのダイレクトマーケティング」について解説いたします。
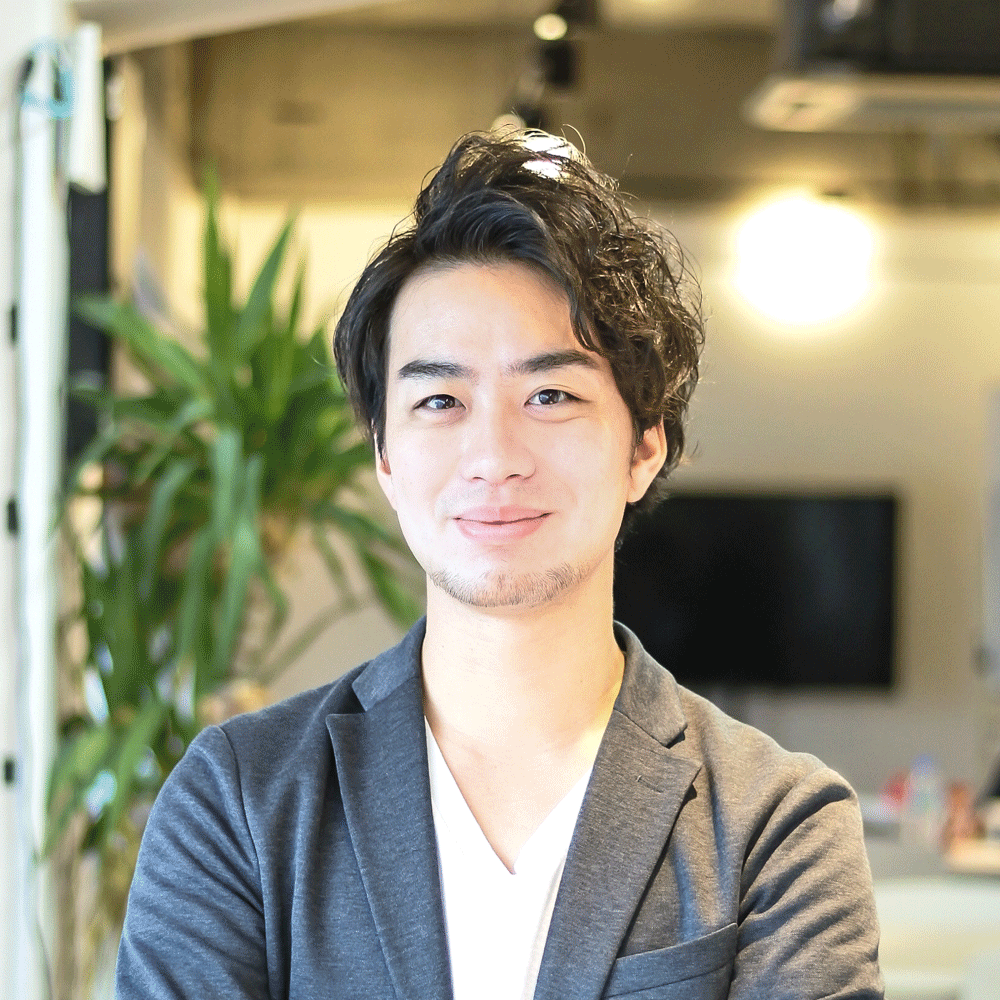 |
小嶋 泰我
Supership株式会社 マーケティング事業本部 プロダクトマーケティング室長 |
※この記事は、雑誌「販促会議」2018年9月号に寄稿させていただいたものを再構成したものです。
カタログからECへのシフトが進む中で…マーケターに求められるスキルは?
従来型のカタログ通販では、“四半期に一度程度、顧客リスト上の消費者にカタログを届け、紙面上で季節ごとのニーズにあわせて自社商品の魅力を伝える”という形をとっていたのに対し、ECでは、Webサイト上で随時(時にはパーソナライズされた)商品が更新され、そのスピード感には決定的な差があります。
Webを用いることによる特性は、以下の3点が挙げられます。
|
これらにより、マーケターに求められるコミュニケーション設計の領域は拡大しており、同時に、消費者へ接触するための選択肢は格段に増えているといえます。
つまり、従来型のカタログ通販からECへシフトしていく中でマーケターに求められるスキルとしては、以下の4点が挙げられます。
|
「自社目線」から「顧客目線」へ
これまでの“非Web型”のダイレクトマーケティングでは、顧客をリスト化し、いかに魅力的なクリエイティブで適切な商品を取り揃えるかが重視されてきました。
しかしながら、インターネットが当たり前となり、日々さまざまな情報に触れてその中から欲しいものだけを“選択”するようになった現代の消費者には、このような「自社目線」の手法では響きません。
情報が溢れる現代においては、「自社目線」ではなく、情報を届けるツール(プラットフォーム)の特性を理解し、活用し得るあらゆるデータを駆使した「顧客目線」のダイレクトマーケティングが求められています。
「顧客目線」のダイレクトマーケティングを実現するためには?
テクノロジーの進化により、従来はダイレクトメールやメールマガジンの反応しか計測できなかったものが、現在では、Web上の行動データから、購入した商品の情報や閲覧情報はもちろん、アトリビューション(間接的な広告効果)まで可視化できるようになりました。
マーケティングにおいてこれらの貴重なデータを活用するためには、顧客と接点を持つことができるプラットフォームの特性などを理解した上で、データを収集して分析し、KPIに基づいたアプローチやターゲットのセグメンテーションを行うことが必要です。
また、非WebとWeb上のダイレクトマーケティングを連携させることも重要であるといえます。従来は、独立したチャネルごとに「短期的にこれくらい売り上げる」といったKPIが設定されることが多くありました。
しかしながら、顧客の視点から考えると、その体験はチャネルごとに分断されているわけではなく、顧客は全チャネルを横断した体験をしているのです。
つまり、チャネルごとに分断された要件定義ではなく、顧客とのタッチポイントとなる全てのチャネルで共有できる指標を持たなければ、「顧客目線」のダイレクトマーケティングを実現するのは難しいといえます。
チャネルが多様化した現代のダイレクトマーケティングでは、ユーザーを軸にしたクロスチャネルでのデータ分析や、顧客コミュニケーションを実現する要件定義が必要です。
横断組織をつくり、マーケティング全体を見渡す
これから社内でダイレクトマーケティングを強化していこうとお考えの場合、様々な部署が連携できるように、横断組織を作るのが望ましいでしょう。そのうえで、マーケティング担当者は“集客担当”という意識から脱却し、“顧客体験の提供者”であるという意識改革を行うべきではないでしょうか。
また、データ分析を行うチームが別にある場合は、そのチームと連携し、まずは体験目線でのユーザーニーズを見極め、それをもとにマーチャンダイジング・サイト設計・集客クリエイティブといった各セクションと連携し、改善を進めていく必要があります。
こうした、横断的なマーケティング組織をまとめる経験値を持つマーケターはそう多くはありません。そのため、社内の誰を担当にすべきか迷うケースも多いと思われますが、
|
以上の3点を満たしている人材が適任といえるのではないでしょうか。
“刈り取り”が売り上げの伸び悩みにつながることも
オンラインでのダイレクトマーケティングでは、短期的な売り上げや獲得単価ばかりを気にしすぎた結果、売り上げに直結するリスティング広告やリターゲティング広告に偏って広告予算を投下してしまうという失敗がよく挙げられます。
こうした、いわゆる“刈り取り”と呼ばれる施策だけを積み重ねた結果、ターゲットの母数が頭打ちとなり、売り上げが伸び悩む企業も増えてきています。
これを回避し、売り上げを伸ばし続けていくためには、既に顕在化/ロイヤル化した顧客だけにアプローチするのではなく、未来の顧客となるユーザーのナーチャリング(育成)や、これまでとは違う市場へのアプローチに注力していく必要があります。
つまり、ダイレクトマーケティングは“短期的な売上を獲得するための施策”ではなく、“中長期的な事業を最大化する施策”であり、組織の中でも注力していくべき領域であると感じています。
“デジタル神話”からの揺り戻しが起きている
いわゆる“デジタル神話”を信じるマーケターの方もいらっしゃるかもしれませんが、Webでは購入しなかった消費者がダイレクトメールにより意思決定が変わったという事例もあり、市場変化という観点では“デジタル神話”からの揺り戻しの流れが来ています。
そういった意味でも、ユーザーのコンテクストを見極めたうえで最適なチャネルを選択することはより重要になっているといえます。特定のチャネル一辺倒の施策ではなく、各チャネルの強みを最大限活かした施策を取り入れることが求められています。
海外市場へ、「KOL」を活用しチャレンジする
新たに開拓する市場として、海外市場が大きな可能性を持っていることには疑いの余地は無いでしょう。特に東南アジアなどでは、日本のようにスマートフォンやSNS文化が定着しており、ダイレクトマーケティングを行いやすい下地がすでに整っています。今後のテクノロジーの進化により、決済や契約、言語の壁に到るまで、進出のハードルはあと数年で飛躍的に下がっていくことが予想されます。
しかしながら、現地に根付く文化や、顧客体験などのソフトウェア領域は、一朝一夕に理解・解決できるものではありません。顧客との接点を持つ様々なマーケターと協力し、顧客理解を深めたうえで市場を開拓していく必要があります。
その一つとして、現地で人気の歌手やタレントを「KOL」(Key Opinion Leader=話題の主軸となるオピニオンリーダー)として起用し、ソーシャルメディア上で一気にリーチを広げ、売り上げを大きく伸ばすことができた事例が挙げられます。従来の広告と比べ、KOLは“人”をメディアとしてリーチするため、共感性が強く、消費者の共感や想起をスピーディーに獲得することができます。
ダイレクトマーケティングで企業の持続的成長を
最後になりますが、「ECに移行すること」はダイレクトマーケティングのゴールではありません。真のゴールは企業の持続的成長であり、ECはその手段の一つしかありません。実現したいゴールを見誤らないよう気をつける必要があります。
しかし、本来の目的である「適切な1to1での顧客コミュニケーションを行うこと」の打ち手としてECを活用し、そこで生まれる顧客コミュニケーションの結果は、間違いなく企業の成長につながるのではないでしょうか。

データマーケティングコンサルティング
Supershipは、データを活用したマーケティングパートナーです。データとテクノロジーでイノベーションを生み出すマーケティングコンサルティングサービスを顧客理解から効果検証まで、ワンストップでご提供しています。
Most Popular
人気記事
Hot Topic
おすすめ記事
-

プロダクト
オンオフデータをシームレスに連携!店舗型リテールメディア「Supership Touch Gift(タッチギフト)」とは?
- 1st Partyデータ活用
- OMO
- Supership Touch Gift
- リテールメディア
-

セミナーレポート
minne byGMOペパボが実践:商品広告を活用した「ECサイトのリテールメディア化」で何が起きた?成功の秘訣とその成果 〜イーコマースフェア 東京 2024セミナーレポート
- S4Ads
-

セミナーレポート
【2023最新版】ゲームアプリ広告収益化のベストプラクティス(Ad Generation講演レポート@ゲームビジネスカンファレンス2023)
- Ad Generation
- SSP
- 動画リワード